(1) 和達−ベニオフ面 (2) 付加体 (3) ホットスボット
(4) 三重会合点 (5) 背弧海盆
---------
推定正解:3
---------
(1) 西南日本と東北日本とを分ける大断層である。
(2) 地表露頭では垂直若しくは急傾斜の断層である。
(3) 西南日本の内帯と外帯を分ける褶曲帯である。
(4) 九州、四国、紀伊半島から関東山地を通って北海道にまで延びている。
(5) 糸魚川一静岡構造線を日本列島の中央部で切断する構造帯である。
---------
推定正解:2
---------
(1) 地震波の初動の押し引き (2) 起震断層の動いた面積
(3) 地震エネルギー (4) 対数表示
(5) 地震波の振幅
---------
推定正解:1
---------
(1) 地温勾配は100℃/kmよりも大きい。
(2) 海溝付近は地殻熱流量が小さい。
(3) 花崗岩の熱伝導度はかんらん岩のそれよりも大きい。
(4) 花崗岩の発熱量もかんらん岩の発熱量も同じである。
(5) 海洋底の年代と地殻熱流量とは無関係である。
---------
推定正解:2
---------
(1) 火山岩を含む地層が水平に回転した。
(2) 火山岩形成後に磁場の強さが変化した。
(3) 火山岩形成後に磁場が逆転した。
(4) 火山岩形成後に磁極が移動した。
(5) 火山岩が現在よりも低緯度で形成された。
---------
推定正解:5
---------
(1) 青色片岩相 (2) プレート沈み込み帯 (3) 藍閃石
(4) 紅柱石 (5) 三波川変成帯
---------
推定正解:4
---------
(1) 高温ガスと固体の混合物である。
(2) 火砕流堆積物は淘汰がよい。
(3) 火砕流堆積物は谷を埋めて堆積する。
(4) 溶岩ドームの崩壊によっても形成される。
(5) 大規模火砕流の噴出にともなってカルデラが形成される。
---------
推定正解:2
---------
(1) 爆発的噴火が起こる。
(2) マグマが完全に固化する際の温度が下がる。
(3) マグマの粘性が下がる。
(4) マグマの密度が大きくなる。
(5) 含水珪酸塩鉱物が形成される。
---------
推定正解:1
---------
(1) Fe2O3+3H2 → 2Fe+3H2O
(2) 4FeO・OH+2C → 4Fe+2CO2+2H2O+O2
(3) Fe3O4+2C → 3Fe+2CO2
(4) 4Fe3O4+O2 → 6Fe2O3
(5) FeS2+2H2O+3O2 → Fe+2H2SO4
---------
推定正解:3
---------
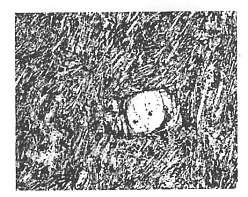
(1) 花崗岩 (2) 玄武岩 (3) 砂岩
(4) 晶質石灰岩 (5) 緑泥片岩
---------
推定正解:2
---------
岩石(母岩)中に生じた割れ目に[ a ]が入り込み、母岩に[ b ]を与えるとともに2種類の鉱物(又は鉱物の組み合わせ)を晶出させ、鉱脈を形成した。その際、割れ目の大きさと晶出する鉱物の量の多寡に応じて[ c ]が形成された。
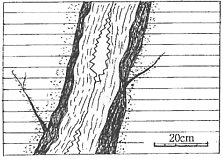
| a | b | c | |
| (1) | 熱 水 | 変 質 | 斑 晶 |
| (2) | 地下水 | 応 力 | 晶 洞 |
| (3) | マグマ | 変 質 | 斑 晶 |
| (4) | マグマ | 応 力 | 斑 晶 |
| (5) | 熱 水 | 変 質 | 晶 洞 |
---------
推定正解:5
---------
(1) 白亜紀の温暖気候 (2) 変成作用 (3) 背斜構造
(4) 高い孔隙率 (5) 海生動物プランクトンの繁殖
---------
推定正解:2
---------
(1) 縞状鉄鉱床(赤鉄鉱、磁鉄鉱、石英)
(2) キースラーガー(黄銅鉱、黄鉄鉱、磁硫鉄鉱)
(3) 斑岩銅鉱床(黄銅鉱、斑銅鉱、輝水鉛鉱)
(4) 黒鉱鉱床(磁鉄鉱、黒鉛、鉄マンガン重石、黒雲母)
(5) スカルン鉱床(ざくろ石、透輝石、磁鉄鉱、黄銅鉱、灰重石)
---------
推定正解:4
---------
(1) 閃亜鉛鉱(燐酸塩)、輝水鉛鉱(硫化物)、蛍石(酸化物)
(2) 赤鉄鉱(硫化物)、石英(酸化物)、燐灰石(元素鉱物)
(3) 黄鉄鉱(酸化物)、錫石(元素鉱物)、方鉛鉱(硫化物)
(4) 磁鉄鉱(酸化物)、黄銅鉱(硫化物)、硫黄(元素鉱物)
(5) 辰砂(元素鉱物)、硫砒鉄鉱(硫化物)、岩塩(酸化物)
---------
推定正解:4
---------
(1) メタノール (2) ブロモフォルム (2) アセトン
(4) 塩酸 (5) モノクロロナフタレン
---------
推定正解:2
---------
鉱物の[ ]は1.4から3.2ぐらいまでの間にある。
顕微鏡下では、[ ]が0.05ぐらい違う場合は一見して区別できる。
薄片は樹脂に封じ込んであるが、樹脂と鉱物の[ ]の差によって薄片での鉱物の見え方が違う。
2つの物質の[ ]の高低を簡単に比ぺるには両者の境のベッケ線を見ればよい。
(1) 比重 (2) 複屈折 (3) 消光位 (4) 屈折率 (5) 熱膨張率
---------
推定正解:4
---------
(1) 石灰岩 (2) 石炭 (3) チョーク (4) チャート (5) ドロマイト
---------
推定正解:3
---------
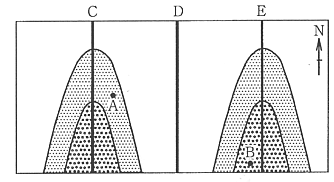
(1) いずれも北に軸傾斜した背斜−向斜−背斜
(2) いずれも北に軸傾斜した向斜−背斜−向斜
(3) CとEは南に、Dは北に軸傾斜した向斜−背斜−向斜
(4) いずれも南に軸傾斜した背斜−向斜−背斜
(5) いずれも南に軸傾斜した向斜−背斜−向斜
---------
推定正解:5
---------
(1) ストロマトライト−原生代−海の浅瀬
(2) フズリナ−古生代−湖の浅瀬
(3) ビカリア−白亜紀−亜熱帯の潮間帯
(4) 貨幣石−古第三紀−亜熱帯の深海
(5) アンモナイト−新第三紀−沖合の海
---------
推定正解:1
---------
(1) 三角州は河川が湖や海に注ぐ所にできる地形であり、堆積作用が活発なので上流側よりも粗粒な礫質堆積物からなっている。
(2) 河岸段丘は日本のような地殻変動の大きい地域に発達する階段状の地形で、標高の高い段丘ほど形成年代が新しい。
(3) 河川が山地から平野に流下するところにできる扇状地は、砂礫質堆積物に富み、網状に分岐・合流した河道が卓越することが多い。
(4) 蛇行河川には河道、突州、自然堤防、氾濫原の地形が発達するが、河道の移動によって上方粗粒化を示す堆積物の積み重なりが形成される。
(5) 上流河川は侵食力が強いので急流ができ、断面がU字状の深い谷ができる。
---------
推定正解:3
---------