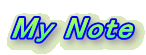

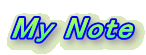 |
精霊達の音 |  |
| 2005.1.18 |
アフリカの「ささやき歌」というのがある。
 |
| 縄文式土笛。 山から粘土を取ってきて、野焼きで焼いた。 材料から仕上げまで、すべて手作りである。 |
ささやくように詩を口ずさむのだが、メロディーはほとんどなく、何と言うか、ラップをひそひそ声で歌っているような感じだ。
ところがこれを、真っ暗な夜に人里離れた山の中で聞くとぞっとするほどいい。精霊のささやき声そのものである。できるだけうっそうとした森の中ならなおいい。
似たようなものに「縄文笛」がある。焼き物の笛で、指穴は1つしかない。
山で赤土を取ってきて、丹念に石をのぞいてすりつぶして粘土を作り、水を混ぜて湿った状態でしばらく寝かせると、縄文土器には最適の粘土になる。温度の不安定な野焼きで焼成するので、収縮しないように3割ほども砂を混ぜる縄文土器は、普通の陶芸用粘土ではかえって不都合で、その辺の山から取ってきた風化土のほうがよほどよい。
私は数年前にこれに凝っていくつも笛を作ったのだが、柔らかい実にいい音がする。演奏法は良く知らないが、指穴のふさぎ具合を連続的に変えるとポルタメントっぽくなる(ちょっとシンセっぽくもなる)。また指穴を速く開け閉めしてトリルすると、楽器というより何かの鳴き声みたいにもなる。
このトリルを真っ暗な夜の森の中でやると、もう本当にぞくっとする。「何か呼んじゃったんじゃないか」と思うほど「森に住むもの」が身近に感じる。
アボリジニの「うなり木」もそうであるが、「楽器」というより「音具」というべきものは、音楽を奏でるのではなく、精霊とかそういった自然の中に潜む「もの」と話をする、あるいは交感するための器具であったのではなかろうか。
夜の闇の中には、確かに何かがいたのである。それは実在するものかもしれないし、人の心の投影であるかもしれない。自然という理解しきれないものの一面をそういう「何か」として実感して畏怖していたのかもしれない。
縄文の時代、「羅生門」の時代、さらに「百鬼夜行」の江戸時代にも、それは精霊であったり魔物であったり妖怪であったりしながら、我々日本人の身近にいたのである。
科学技術に支えられて、危険な動物を遠ざけ、夜の闇からわが身を遠ざけ、医療の発達や核家族化によって死さえも身近ではなくした我々。もちろん夜オオカミに襲われるのはイヤだし、暖かいところで長生きしたいけれど、ちょっと無味乾燥な気もするのである。
また暖かくなったら、夜の浜で焚き火を囲もう。気のおけない仲間達と網で新鮮な魚や野菜を焼き、うまい酒を飲み、話が尽きたら焚き火の炎をじっと眺めているだけでいい。
2005.1.18 ブログに掲載